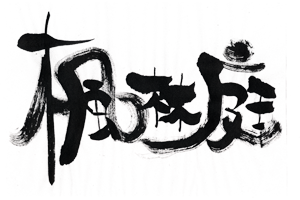楓林庭コラム 2025.9.29
こんにちは
『暮らしに本当に合う外構』を一緒に考え、丁寧にかたちにしていくことを大切にしています「fuurintei」です
今回のテーマは
『芝生再生チャレンジ中 ― 小さな芽から始まる物語』
実は枯らしてしまいまして…。でも…
植物を育てていると、思うようにいかないこともあります
気づけば茶色く変色し、「もうダメかも」と諦めそうになる瞬間
今回もまさにそんな状態で、根元近くまでカットして様子を見ていたのですが、水をあげすぎてしまったのか、今度はカビが発生してしまいました

この芝生は、先日メニコンさんからいただいた在来コウライシバ(写真右側)のサンプル品
もともとは写真のように、ふさふさと元気で美しい緑をしていました
この在来コウライシバは葉丈の短い芝生『ナルオターフ』との伸び具合を比較するために大切に育てていたのですが、ある朝出勤してみると、なんと茶色く枯れかけてしまっていたのです

「やってしまった…」と一旦落ち込み、
「これはいかん!」と次は慌てて、まずは根元近くまで刈り込み水をしっかり与えて様子を見ることにしました


ところが今度は水のやりすぎでカビが発生…
焦れば焦るほど裏目に出るようで、正直、がっかりする気持ちもありました
それでも、よく見ると枯れ色の中から小さな新芽が顔を出しているんです
「まだ生きてる!」と嬉しくなり、その姿がいじらしくてどうにかこの子を助けたい、もう一度ふさふさの緑を取り戻したい!という気持ちになりました
そこで、一回り大きなポットに植え替え、底には石を敷いて通気性を確保
新しい芽のない部分は思い切って根元までカットし、今度は外に出して自然の光と風にあてて様子を見ることにしました


まだまだ“途中経過”ではありますが、小さな芽が育っていく姿は、庭づくりにおける一番のご褒美
植物は簡単には諦めないし、その再生力を信じてあげることが大切なのだと、改めて気づかされます
これからどうなるか分かりませんが、この芝生のリカバリー(回復)ストーリーを少しずつ記録していけたらと思っています
小さな芽を見守る時間は、庭にいるひとときをより豊かにしてくれますね
在来コウライシバについて
在来コウライシバ(ヒメコウライシバ) は、日本の気候風土に古くから適応してきた代表的な芝生のひとつです
特に庭園や校庭、公共の広場など幅広く利用されてきました
特長
-
葉の質感:細く柔らかい葉を持ち、見た目にも繊細で和の庭にもよく調和します
-
耐暑性:高温多湿の日本の夏に強く、猛暑の中でも比較的安定して生育します
-
踏圧への強さ:地面を這うように横へ広がり、ある程度の踏みつけにも耐えられる強さを備えています
弱点
-
冬期の休眠:冬になると地上部は茶色く枯れ込む休眠期に入るため、一年中青々とした芝生を維持することはできません
-
成長スピード:西洋芝に比べると成長はゆっくりで、ふさふさとした芝面をつくるには時間と継続的な手入れが必要です
管理のポイント
-
刈り込み:密度を高め、見た目を整えるために定期的な芝刈りが欠かせません
-
目土入れ:芽数を増やし、凹凸を解消するために春や秋に行うと効果的です
-
水やり:基本的には乾燥した時期に補う程度でよく、水の与えすぎは根腐れやカビの原因となります
在来コウライシバは、西洋芝に比べると派手さや通年の緑は劣りますが、**「日本の庭に馴染む落ち着いた芝生」**を楽しめるのが大きな魅力です
育成には時間と根気が求められますが、その分だけ愛着の湧く芝といえるでしょう
芝刈りがほぼ不要?「ナルオターフ」については
温暖化の時代に外構会社が届けたい天然芝「ナルオターフ」の魅力
↑こちらの記事も併せてご参照ください